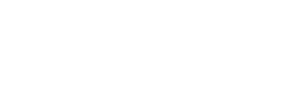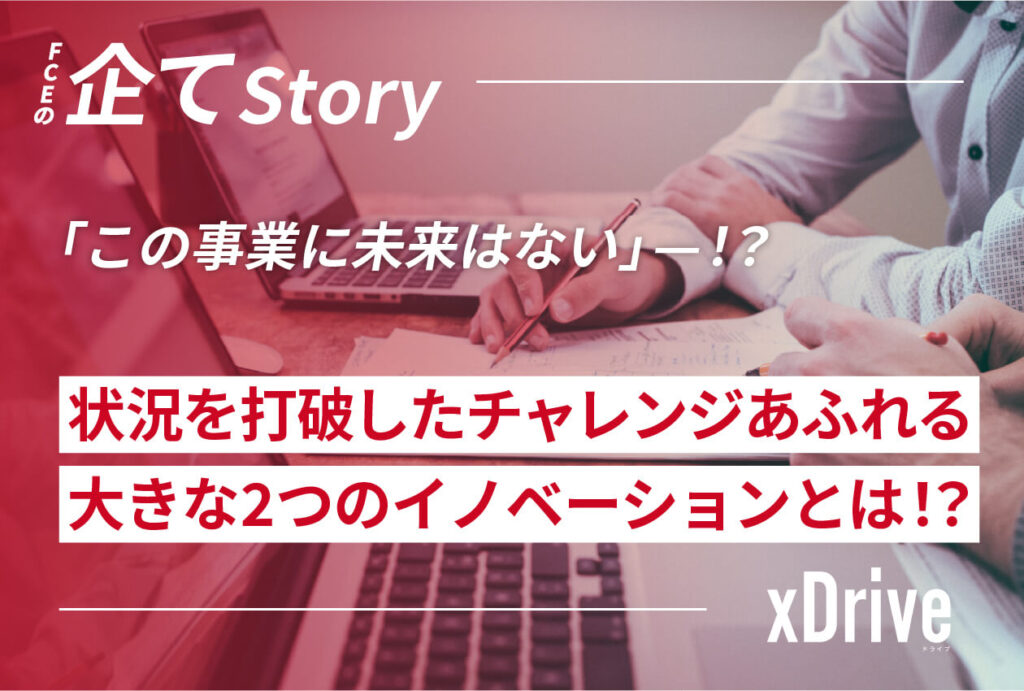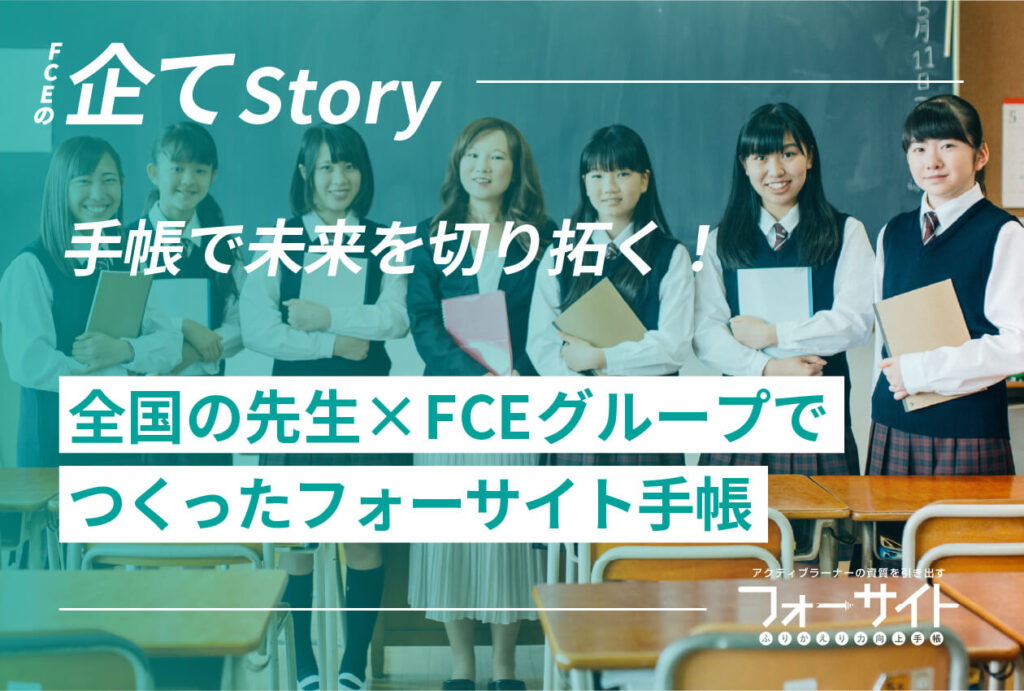#企業家のクワダテ
FCEは“企”業家集団。
企業家とは、業を“起”こすのではなく、業を “企て”ること。
FCE„ÅåÂÆöÁæ©„Åô„Çã‚Äú‰ºÅ„Ŷ‚Äù„ÅØ„Äʼn∫ãÊ•≠„ÇíÁ´ã„Å°‰∏ä„Åí„Åü„ÇäÊñ∞ÂïÜÂìÅ„ÇíÈñãÁô∫„Åó„Åü„Çä„Å®„ÅÑ„Å£„Åü§ß˶èÊ®°„Å™„ÇÇ„ÅÆ„ÅÝ„Åë„ÇíÊåá„Åô„ÅÆ„Åß„ÅØ„Å™„Åè„ÄÅ
Ë∫´Ëøë„řʕ≠Âãô„ÇíÊîπÂñÑ„Åó„Åü„Çä„ÄÅÂæìÊù•„ÅÆËÄÉ„ÅàÊñπ„Çí§â„Åà„Ŷ„Åø„ŶÁîü„Åæ„Çå„ÇãÂ∞è„Åï„Å™„ǧ„Éé„Éô„ɺ„Ç∑„Éß„É≥„ÅÝ„Å£„Åü„Çä„ÄÇ
「今よりもっと、次をよいものにしていくための取り組み」を“企て”としています。
そこに社歴、年齢、所属は関係ありません。
本企画は、FCEの企業家たちをご紹介します!
¬Ý
♦ÁõÆʨ°♦¬Ý
¬Ý
1.「役に立つ」をタイミングよく届けたい──マーケティングという仕事
2.営業職1年目──何もできず、悩み抜いたスタートライン
ÔºìÔºé‚Äú„Åß„Åç„Çã„Åì„Å®‚Äù„Ç퉪ïÁµÑ„Åø„Å´„Åô„Çã‚îÄ‚îÄÁßÅ„ÅåÂûãÂåñ„Å´„Åì„ÅÝ„Çè„ÇãÁêÜÁî±
4.マーケティング配属後の試練と転機
5.「リーダーを勝たせる」フォロワーシップと主体性のバランス
Ôºñ. ʨ°„Å™„Çã„ÇØ„ÉØ„ÉÄ„ÉÜÔΩû„Äå„Ç≥„É≥„Éà„É≠„ɺ„É´„Åß„Åç„ÇãÈÝòÂüü„Çí„ÇÇ„Å£„Ů¢ó„ÇÑ„Åó„Åü„ÅÑ„Äç
今回は、トレーニング・カンパニー事業本部でマーケティングを担当する瀬山さんにお話を伺いました。

ÁĨ±±„Åï„Çì„ÅØ„ÄÅ„Å®„Å´„Åã„Åè‰∏ÄÁ∑í„Å´‰ªï‰∫ã„Çí„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã‰∏äÂè∏„ɪÂêåÂÉöÁ§æÂì°„Åã„Çâ„ÅÆË©ï‰æ°„ÅåÁ¥ÝÊô¥„Çâ„Åó„ÅÑÔºÅ
トレーニング・カンパニー 上司・宇田川さんよりコメント
守備範囲の広さとそれを可能にする物事を整理して身につける力がすごいと思います。
„É°„É´„Éû„Ǩ„ÅÆË®≠Ë®à„ÄÅÈÖç‰ø°„ÄúPR„Äʼn∫ã‰æã„ǧ„É≥„Çø„Éì„É•„ɺ„Å™„Å©„ÄÅÂπÖÂ∫É„ÅÑÂÆàÂÇôÁØÑÂõ≤„Çí„Ç´„Éê„ɺ„Åó„Å™„Åå„Çâ„Äʼn∏ÄÈÉ®„É°„É≥„Éê„ɺ„ÅÆ„Éû„Éç„Ç∏„É°„É≥„Éà„Åæ„Å߉ªª„Åõ„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„Åå„ÄÅ„Åì„ÅÆÁØÑÂõ≤„Ç퉪ª„Åõ„Çâ„Çå„ÇãÂÆâÂøÉÊÑü„Åå„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„Åå„ÄÅÊú¨ÂΩì„Å´Á¥ÝÊô¥„Çâ„Åó„ÅÑ„Å™„Å®ÊÄù„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Åù„Åó„Ŷ„ÄÅ„Åù„Çå„Çâ„ÅØ„ÇÇ„Å®„ÇÇ„Å®ÈÅ©ÊÄß„Åå„ÅÇ„Å£„Åü„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Çà„Çä„ÅØ„ÄÅ„Åù„Çå„Åû„ÇåÂÉï„Å´ËÅû„ÅÑ„Åü„Çä„Äʼnªñ„Çπ„É܄ɺ„ÇØ„Éõ„É´„ÉĄɺ„Å´Á¢∫Ë™ç„Åó„Åü„Çä„ÄÅËá™ÂàÜ„ÅßÂûã„Çí‰Ωú„Å£„Åü„Çä„Åó„Ŷ„Äʼn∏Ąŧ„Åö„ŧÁùÄÂÆü„Å´Ëá™ÂàÜ„ÅÆ„ÇÇ„ÅÆ„Å´„Åó„Ŷ„Åç„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Åß„Åô„ÄÇ
物事を、感覚的にではなく、誰でも理解できる状態に整理して身につけていく力、吸収力と整理力みたいなものが、すごいなと感じています。
トレーニング・カンパニー 上司・藤原さんよりコメント
ÁĨ±±„Åï„Çì„ÅÆ„Åô„Åî„ÅÑ„Å®„Åì„Çç„ÅØ„ÄÅ„Åæ„ÅöË™ÝÂÆü„Åï„ÄÇ
FCE„ÅÆË™ÝÂÆü„Å®„ÅØÂòò„ŧ„Åç„ÄÅÊ≠£Áõ¥„ÄÅË™ÝÂÆü„ÅÆ„Å™„Åã„Åß„ÄÅË™ÝÂÆü„Å®„ÅØË®ÄËëâÔºàÂƣˮÄÔºâ„Ů˰åÂãï„ÇíÂêà„Çè„Åõ„Çã‰∫ã„Åß„Åô„Åå„Åæ„Åï„Å´ÁĨ±±„Åï„Çì„ÅØË™ÝÂÆü„ř˰åÂãï„Çí„Åó„Ŷ„Åè„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ
‰æã„Åà„Å∞‰ºöË≠∞„Å´„Åä„ÅфŶÁõõ„Çä‰∏ä„Åå„Çäʨ°„ÅƉ∏ÄÊâã„Åå„ŵ„Çè„Å£„Å®„Åó„Ŷ„Åó„Åæ„Å£„Ŷ„ÇÇ„ÄÅ„Åï„Å£„Å®ÂÝ¥„Ç퉪ïÂàá„ÇäÊòéÁ¢∫„Å´„Åó„Ŷ„Åè„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„ÅØÁĨ±±„Åï„Çì„ÅåÊòéÁ¢∫„Ŵʨ°„ÅƉ∏ÄÊâã„ÇíÊòéÁ¢∫„Å´„Åô„Çã„Å®„ÅÑ„ÅÜË™ÝÂÆü„Åï„ÅÆË≥úÁâ©„Åß„Åô„ÄÇPR„ÇÑIR„ÇÇÂêåÊßò„Åß„Åô„Åó„ÄÅ„É°„É´„Éû„Ǩ„Å™„Å©„ÇÇÂêåÊßò„Å´Ë™ÝÂÆü„Å´ÂØæÂøú„Åó„Ŷ„Åè„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
そして、プロフェッショナル(安定感)であること。
‰∏äË®ò„Åƪ∂Èï∑„Åß„ÇÇ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„Åå„ÄÅÁĨ±±„Åï„Çì„ÅåÊú¨ÂΩì„Å´„Åô„Åî„ÅÑ„Å™„Å®ÊÄù„ÅÜ„ÅÆ„ÅØÂèó„Åë„Åü‰ªï‰∫ã„Çí„Åó„Å£„Åã„Çä„Å®ÈÅÇË°å„Åô„Çã„Åì„Å®„Åß„Åô„ÄÇ„Åæ„Åï„Å´„Éó„É≠„Éï„Çß„ÉÉ„Ç∑„Éß„Éä„É´„ÅÝ„Å™„Å®ÊÑü„Åò„Åæ„Åô„ÄÇÊïÖ„Å´ÂÆâÂÆöÊÑü„ÇÇ„ÅÇ„ÇäÂÆâÂøÉÊÑü„ÇÇ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
ブランド戦略グループ 安宅さんよりコメント
瀬山さんとは部署こそ違えこそ、PRで連携することが多いです。
瀬山さんのすごさを語れば軽く2000文字は超えてしまいそうなのですが…
Á¥ÝÊô¥„Çâ„Åó„ÅÑ„Å™„Å®ÊÄù„ÅÜ„Åì„Å®„ÅƉ∏Ąŧ„Å剪ï‰∫ã„ÅƉªïÊñπ„Åß„Åô„ÄÇ
‰æã„Åà„Å∞„ÄÅÁĨ±±„Åï„Çì„Åã„Çâ„ÅƉæùÈݺ„É°„ɺ„É´„ÅØ„Åô„Åπ„Ŷ„ÉÜ„É≥„Éó„ɨ„ɺ„ÉàÂåñ„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
故に、いつまでに、何を、どんな目的ですればいいのかすごくわかりやすい。
„Åæ„ÅüÁü≠Á¥çÊúü„Åß„ÅƉæùÈݺ„ÅåÊù•„Çã„Åì„Å®„Å؄Ū„ź„Å™„Åè„ÄÅÂ∏∏„Å´Á¥çÊúü„Å´‰ΩôË£ï„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åì„Çå„ÅØ„ÄÅÁĨ±±„Åï„ÇìËá™Ë∫´„ÅåÊÄùËÄÉÈåØË™§„ÅƉ∏≠„Åã„Çâ„ÄÅÈáç˶ńř˶ÅÁ¥Ý„ÇíÊ¥ó„ÅÑÂá∫„Åó„Äʼnªï‰∫ã„ÅƉªïÊñπ„ÇÑÈÄ≤„ÇÅÊñπ„ÇíÊ®ôÊ∫ñÂåñ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åã„Çâ„ÅÝ„Å®ÊÄù„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åì„ÅÜ„Åó„Åü‰∏Ąŧ‰∏Ąŧ„ÅƉªï‰∫ã„Å´ÁúüÂ⣄ŴÂèñ„ÇäÁµÑ„Åø„ÄÅ„Åù„ÅÆÂäπÊûú„ÇíÊúħßÂåñ„Åï„Åõ„Çã„Åü„ÇÅ„Å´Â∑•Â§´„Å®Âä™Âäõ„Çí„Åô„Çã„Åì„Å®„ÄÅ„Åù„Çå„ÅåÁĨ±±„Åï„Çì„Åƺ∑„Åø„ÅƉ∏Ąŧ„ÅÝ„Å®ÊÄù„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
¬Ý
È´òË©ï‰æ°„ÅƵê‚Ķ„Åù„Çì„Å™ÁĨ±±„Åï„Çì„ÅÆÂßøÂ㢄ÄÅÈÝ≠„ÅƉ∏≠„Å´Ëø´„Çä„Åæ„ÅôÔºÅ
「役に立つ」をタイミングよく届けたい──マーケティングという仕事
¬Ý
――現在、どのような業務を担当されているのですか?
¬Ý
ÁĨ±±ÔºöÊ≥ï‰∫∫Âêë„Åë„Å´Á§æÂì°ÊïôËÇ≤„ɪ‰∫∫Ë≤°ËÇ≤Êàê„ÅƉ∫ãÊ•≠„Çí±ïÈñã„Åô„Çã„Éà„ɨ„ɺ„Éã„É≥„Ç∞„ɪ„Ç´„É≥„Éë„Éã„ɺ‰∫ãÊ•≠Êú¨ÈÉ®„Å´Êâıû„Åó„Ŷ„ÅфŶ„ÄÅ„Éû„ɺ„DZ„ÉÜ„Ç£„É≥„Ç∞ÈÝòÂüü„ÇíÂÖ®Ëà¨ÁöÑ„Å´ÊãÖÂΩì„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
トレーニング・カンパニーでは「働くをもっとおもしろくする」を事業パーパスとして、Smart Boardingを始め様々な人財育成に関わる商材をお客様に提供しています。
ÁßÅ„ÅÆÂΩπÂâ≤„ÅØ„ÄÅ„Çà„Çä§ö„Åè„ÅÆÁµåÂñ∂ËÄÖ„Çщ∫∫‰∫ã„ÅÆ„ÅäÂÆ¢Êßò„Å´Ë™çÁü•„ɪËààÂë≥Èñ¢ÂøÉ„ÇíÊåÅ„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÅÝ„Åè„Åì„Å®„ÄÇ„Åù„ÅÆ„Åü„ÇÅ„Å´„É°„ɺ„É´ÈÖç‰ø°„Çщ∫ã‰æã„ǧ„É≥„Çø„Éì„É•„ɺ„ÄÅPR„ÄÅHP„Å´Êé≤˺â„Åô„Çã„Åü„ÇÅ„ÅÆÈ°ßÂÆ¢„É≠„Ç¥ÂõûÂèé„ÄÅÂ∞éÂÖ•„É™„É™„ɺ„Çπ„ÄÅÂÖ±ÂǨ„Ǫ„Éü„Éä„ɺ„Å™„Å©„Äʼn∏ª„Å´5„ŧ„ÅÆÊñΩÁ≠ñ„ÇíÂãï„Åã„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
‚Äï‚Äï„Åã„Å™„ÇäÂπÖÂ∫É„ÅÑÈÝòÂüü„Åß„Åô„Å≠„ÄÇ„Åù„Çå„Çâ„ÅƉªï‰∫ã„ÅƉ∏≠„Åß„ÄÅÁâπ„Ŵ§߉∫ã„Å´„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã‰æ°Âħ˶≥„ÅØ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÅãÔºü
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö‰∏ÄË≤´„Åó„ŶÊÑèË≠ò„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÅÆ„ÅØ„ÄÅ„Äå„ÅäÂÆ¢Êßò„Å´„Å®„Å£„Ŷ„ÄÅ‚ëÝÂΩπ„Å´Á´ã„ŧÊÉÖÂݱ„Çí„ÄÅ‚ë°ÂàÜ„Åã„Çä„ÇÑ„Åô„Åè„Äł뢄Çø„ǧ„Éü„É≥„Ç∞„Çà„Åè±ä„Åë„Çã„Åì„Å®„Äç„Åß„Åô„ÄÇ
„Åì„ÅÆ3„ŧ„ÅåÊèÉ„Å£„Ŷ„ÅÑ„Å™„ÅÑ„Å®„ÄÅ„Å©„Çå„ÅÝ„ÅëËâØ„ÅÑÊÉÖÂݱ„Åß„ÇÇÁõ∏Êâã„Ŵ±ä„Åã„Å™„ÅÑ„Å®ÊÄù„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
¬Ý
――“タイミングよく”というのは?
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„Åü„Å®„Åà„Å∞„Äʼnªä„Åæ„Åï„Å´„Ç´„É°„É©„Çíʨ≤„Åó„ÅÑ„Å®ÊÄù„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã‰∫∫„Å´„Äå„Åì„ÅÆ„Ç´„É°„É©„ÅÑ„ÅÑ„Åß„Åô„Çà„Äç„Å®ÊÉÖÂݱ„Åå±ä„Åë„Å∞„ÄÅ„Åô„Åê„Å´ÂèçÂøú„Åó„Ŷ„ÇÇ„Çâ„Åà„Åæ„Åô„Çà„Å≠„ÄÇ„Åß„ÇÇ„ÄÅÊÉÖÂݱ„Åå±ä„Åè„ÅÆ„Åå1Âπ¥Ââç„ÅÝ„Å£„Åü„Çâ„Äå„ŵ„ɺ„Çì„Äç„ÅßÁµÇ„Çè„Çã„Åã„ÇÇ„Åó„Çå„Å™„ÅÑ„ÄÇ„ÅÝ„Åã„Çâ„Åì„Åù„ÄÅ„Äå„ÅäÂÆ¢Êßò„Å剪ä„ÄÅËààÂë≥„ÇíÊåÅ„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åì„Å®„Äç„ÇíÊçâ„Åà„Ŷ±ä„Åë„Çã„Å®„ÅÑ„ÅÜ‚Äú„Çø„ǧ„Éü„É≥„Ç∞‚Äù„Åå„Åô„Åî„ÅèÈáç˶ńř„Çì„Åß„Åô„ÄÇ
¬Ý
‚Äï‚Äï„ÄåÂàÜ„Åã„Çä„ÇÑ„Åô„Åè±ä„Åë„Çã„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜÁÇπ„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÇÇ„ÄÅ„Åì„ÅÝ„Çè„Çä„Åå„ÅÇ„Çã„ÅÆ„Åß„Åô„Å≠„ÄÇ
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅØ„ÅÑ„ÄÇ„ÅäÂÆ¢Êßò„Å´„Å®„Å£„Ŷ„ÅÆ‚ÄúÂàÜ„Åã„Çä„ÇÑ„Åô„Åï‚Äù„Å£„Ŷ„ÄÅ„Åì„Å°„Çâ„ÅåÊÄù„Å£„Ŷ„ÅÑ„Ç㉪•‰∏ä„Å´„Éè„ɺ„Éâ„É´„ÅåÈ´ò„ÅÑ„Çì„Åß„Åô„ÄÇÈõ£„Åó„ÅÑÂ∞ÇÈñÄÁî®Ë™û„ÇÑÊ•≠ÁïåÁî®Ë™û„Åå‰∏¶„Çì„Åß„ÅÑ„Çã„Å®„ÄÅ„Åù„Çå„ÅÝ„Åë„ÅßË™≠„ÇÄÊ∞ó„Å姱„Åõ„Ŷ„Åó„Åæ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Å™„ÅÆ„Åß„ÄÅ„Å™„Çã„Åπ„ÅèÊó•Â∏∏‰ºöË©±„Å´Ëøë„ÅÑ„Éà„ɺ„É≥„Åß„ÄÅ„Åß„ÇÇÂÜÖÂÆπ„ÅÆÊú¨Ë≥™„ÅØ„Éñ„ɨ„Å™„ÅÑ„Çà„ÅÜ„Å´Êõ∏„Åè„Å®„ÅÑ„ÅÜ„ÅÆ„ÅØ„ÄÅÂ∏∏„Å´ÊÑèË≠ò„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
¬Ý
――マーケティングは手段が多様ですよね。メール、ウェブ、広告、イベント…。それをどう選び、どう組み合わせているのでしょう?
¬Ý
瀬山:まさにそこがマーケティングの難しさであり、面白さでもあります。手段は本当にたくさんある中で、目的とターゲットに合わせて最適な組み合わせを考えるのが役割です。たとえば展示会や広告などは広く認知を取るのに適していますが、商談や導入に近いフェーズであれば、事例インタビューや共催セミナーのほうが刺さりやすいです。

――その5つの施策をどのように展開しているのですか?
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„É°„ɺ„É´ÊñΩÁ≠ñ„ÅßÊÉÖÂݱ„Çí±ä„Åë„ÄÅËààÂë≥„ÇíÊåÅ„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÅÝ„ÅÑ„ÅüÊñπ„Å´„Å؉∫ã‰æã„ǧ„É≥„Çø„Éì„É•„ɺ„ÇÑÂ∞éÂÖ•„É™„É™„ɺ„Çπ„ÇíÈÄö„Åó„Ŷ„Äå„É™„Ç¢„É´„ř£∞„Äç„Ç퉺ù„Åà„Çã„ÄÇ„Åù„Åó„Ŷ„Äå„ÇÇ„Å£„Ů˩≥„Åó„ÅèÁü•„Çä„Åü„ÅÑ„Äç„Å®ÊÄù„Å£„Ŷ„Åè„ÅÝ„Åï„Å£„ÅüÊñπ„Å´„ÅØÂÖ±ÂǨ„Ǫ„Éü„Éä„ɺ„ÇÑÂñ∂Ê•≠„Å®„ÅÆÈù¢Ë´á„Å´„ŧ„Å™„Åí„ŶÁõ¥Êé•„ÅäË©±„ÇíËÅû„ÅфŶ„ÅÑ„Åü„ÅÝ„Åè„ÄÇ„Åô„Åπ„Ŷ„ÅÆÊñΩÁ≠ñ„ÅåÁÇπ„Åß„ÅØ„Å™„ÅèÁ∑ö„Å߄ŧ„Å™„Åå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´ÊÑèË≠ò„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
¬Ý
‚Äï‚ÄïÊÉÖÂݱ„ÅÆË≥™„ÅÝ„Åë„Åß„Å™„Åè„ÄÅË®≠Ë®à„ÅÆÂÖ®‰ΩìÂÉè„Åæ„ÅßËÄÉ„Åà„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÅÆ„Åß„Åô„Å≠„ÄÇ
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅØ„ÅÑ„ÄÇ„Äå±ä„Åë„Åü„ÅÑÊÉÖÂݱ„Çí„ÄÅ„Å©„ÅÜ„Åô„Çå„Å∞±ä„Åè„Åã„Äç„ÇíË®≠Ë®à„Åô„Çã„ÅÆ„Åå„Éû„ɺ„DZ„ÉÜ„Ç£„É≥„Ç∞„ÅƉªï‰∫ã„ÅÝ„Å®ÊÄù„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
¬Ý
営業職1年目──何もできず、悩み抜いたスタートライン
‚Äï‚ÄïÁèæÂú®„ÅØ„Éû„ɺ„DZ„ÉÜ„Ç£„É≥„Ç∞„ÅƉ∏≠ÊÝ∏„ÇíÊãÖ„ÅÜÁĨ±±„Åï„Çì„Åß„Åô„Åå„ÄÅÊúÄÂàù„ÅÆ„Ç≠„É£„É™„Ç¢„ÅØÂñ∂Ê•≠„ÅÝ„Å£„Åü„Å®‰º∫„ÅÑ„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅØ„ÅÑ„ÄÇ1Âπ¥ÁõÆ„ÅØÊõ∏Á±ç„Äé7„ŧ„ÅÆÁøíÊÖ£„Äè„ÇíÊ≥ï‰∫∫Âêë„Åë„Å´ÁÝî‰øÆ„Å´„Åó„Åü„ÄåÔºó„ŧ„ÅÆÁøíÊÖ£„ÄçÁÝî‰øÆ„ÅÆÂïÜÊùê„ÇíÊⱄÅÜ„Éńɺ„ÉÝ„Å´Êâıû„Åó„Ŷ„Äńǧ„É≥„ǵ„ǧ„Éâ„Ǫ„ɺ„É´„Çπ„Å®Âñ∂Ê•≠„ÇíÊãÖÂΩì„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Åü„ÅÝ„ÄÅÂΩìÊôÇ„ÅØ„ÄåÊàêÊûú„ÅåÂá∫„Å™„ÅÑ„Äç„Åì„Å®„Å´„Å®„Ŷ„ÇÇË㶄Åó„Åø„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
¬Ý
‚Äï‚ÄïÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å´„ÅØ„ÄÅ„Å©„Çì„Å™Áä∂Ê≥Å„ÅÝ„Å£„Åü„ÅÆ„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÅãÔºü
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ǧ„É≥„ǵ„ǧ„Éâ„Ǫ„ɺ„É´„Çπ„Åß„ÅØ„Ç¢„Éù„ǧ„É≥„Éà„ÇíÂèñ„Çã„ÅÆ„Å剪ï‰∫ã„ÅÝ„Å£„Åü„Çì„Åß„Åô„Åë„Å©„ÄÅÂêåÊúü„Å®ÊØî„Åπ„Ŷ„ÇÇ„Å™„Åã„Å™„Åã„Ç¢„Éù„ǧ„É≥„Éà„ÅåÂèñ„Çå„Å™„ÅÑ„Älj∏äÂè∏„ÅåÂñ∂Ê•≠„Åô„ÇãÈöõ„Å´„ÅØÂêåË°å„ÇÇ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åë„Çå„Å©„ÄÅËá™ÂàÜ„Å剪ª„Åï„Çå„ÇãÂÝ¥Èù¢„ÅØÂ∞ë„Å™„Åè„ÄÅ„ÄåÊàêÊûú„ÇíÂá∫„Åó„Ŷ„ÅÑ„ÇãÂÆüÊÑü„Äç„Åå„Åæ„Å£„Åü„Åè„Å™„Åã„Å£„Åü„Çì„Åß„Åô„ÄÇ
¬Ý
‚Äï‚ÄïÂ뮄Çä„ÅÆÂêåÊúü„Åü„Å°„ÅØ„Å©„ÅÜ„ÅÝ„Å£„Åü„ÅÆ„Åß„Åô„ÅãÔºü
¬Ý
ÁĨ±±ÔºöÂêåÊúü„Å´„ÅØ„Åô„Åî„ÅèÂÄãÊÄß„Ååº∑„Åè„ŶÊàêÊûú„ÇíÂá∫„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„É°„É≥„Éê„ɺ„Åå§ö„Åè„Ŷ„ÄÅÊ≠£Áõ¥„Åô„Åî„ÅèÁѶ„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„ÄåÂêπÁî∞„ÅØ„Ç´„É™„Çπ„ÉûÊÄß„Åå„ÅÇ„Çã„Åó„ÄÅÂè§Èáé„ÅØÈù¢ÁôΩ„Åè„Ŷ„ɶ„Éã„ɺ„ÇØ„ÄÅÊ®™Áî∞„ÅØÊÉÖÁܱÁöÑ„Åß„ÄÅÁü≥ʣƄÅØÂèØÊÑõ„Åè„Ŷ„ÇÆ„É£„ÉÉ„Éó„Åå„ÅÇ„Çã„ÄǧßÈáé„Åا©ÁÑ∂„ÅÝ„Åë„Å©„Ç≠„É©„Ç≠„É©„Åó„Ŷ„ÅфŶ‚Ķ„Äç„Å£„Ŷ„ÄÇ„Åù„Çì„Å™‰∏≠„Åß„ÄåËá™ÂàÜ„Å؉Ωï„Åå„Åß„Åç„Çã„ÅÆÔºü„Äç„Å£„Ŷ„ÄÅ„Åö„Å£„Å®ËÄÉ„Åà„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åó„Åü„ÄÇÁßÅ„ÄÅ„ÇÅ„Å°„ÇÉ„Åè„Å°„ÇÉÂá°‰∫∫„ÅÝ„Å™„Å£„Ŷ„ÄÇ
¬Ý
‚Äï‚Äï„Åù„ÅÆÈÝÉ„ÄÅ„Å©„Çì„Å™ÂøÉ¢ɄÅß„Åó„Åü„ÅãÔºü
¬Ý
瀬山:本当にしんどかったです。しかもその時期はコロナ禍でずっとリモートで、誰にも相談できない。成果も出ないし、正直「仕事が辛い」とさえ思っていました。
¬Ý
――その状況からどうやって抜け出していったのでしょう?
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„Åù„Çì„Å™‰∏≠„ÅßÂî؉∏Ä„ÄÅ„Äå„Åì„Çå„Å™„ÇâËá™ÂàÜ„Åß„ÇÇ„Åß„Åç„Çã„Åã„ÇÇ„Äç„Å®ÊÄù„Åà„Åü„ÅÆ„Åå„ÄÅ„ÅäÂÆ¢Êßò„Å∏„ÅƄǧ„É≥„Çø„Éì„É•„ɺ„Åß„Åó„Åü„ÄÇ„ÄåÔºó„ŧ„ÅÆÁøíÊÖ£¬Æ„Äç„ÅÆÁÝî‰øÆ„ÇíÂèó„Åë„Ŷ„Åè„ÅÝ„Åï„Å£„ÅüÊñπ„ÄÖ„Å´„Äå„Åù„ÅÆÂæå„Å©„ÅܧâÂåñ„Åó„Åæ„Åó„Åü„ÅãÔºü„Äç„Ů˩±„ÇíËÅû„Åç„ÄÅ„Åù„Çå„ÇíË®ò‰∫ã„Å´„Åæ„Å®„ÇÅ„Çã„Å®„ÅÑ„ÅÜÊ•≠Âãô„Åß„Åó„Åü„ÄÇ
¬Ý
――それが、のちのキャリアにつながる転機になったのですね。
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅØ„ÅÑ„ÄÇÂΩìÊôÇ„ÅØ„Åæ„ÅÝ„ÄåÂûãÂåñ„Åô„Çã„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜËÄÉ„Åà„ÇÇ„Å™„Åã„Å£„Åü„ÅÆ„Åß„ÄÅÊñáÁ´Ý„Çí„Åæ„Å®„ÇÅ„Çã„ÅÆ„ÇÇ„Å®„Ŷ„Çǧߧâ„Åß„ÄÅ1Êú¨„ÅÆË®ò‰∫ã„Çí‰Ωú„Çã„ÅÆ„Å´5„Äú6ÊôÇÈñì„Åã„Åã„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Åß„ÇÇ„ÄÅ„Åù„ÅƄǧ„É≥„Çø„Éì„É•„ɺ„ÇíÈÄö„Åó„Ŷ„ÄÅ„ÅäÂÆ¢Êßò„ÅƧâÂåñ„ÅåÁõƄŴ˶ã„Åà„Ŷ‰ºù„Çè„Å£„Ŷ„Åè„Çã„Åì„Å®„Å´„ÄÅ„ÇÇ„ÅÆ„Åô„Åî„Åè‰æ°Âħ„ÇíÊÑü„Åò„Åü„Çì„Åß„Åô„ÄÇ
¬Ý
――具体的に、どのようなエピソードが印象に残っていますか?
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅÇ„Çã„ÅäÂÆ¢Êßò„ÅØ„ÄÅÁÝî‰øÆ„ÇíÂèó„Åë„ÅüÂæå„Å´„ÄåÊÅØÂ≠ê„Å®Â∞ÜÊù•„Å´„ŧ„ÅфŶ˩±„Åô„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü„Äç„Å®Êïô„Åà„Ŷ„Åè„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Åù„Çå„Åæ„Åß„Åü„ÅÝÈáéÁêÉ„ÇíÂøúÊ襄Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åë„Çå„Å©„ÄÅÊÅØÂ≠ê„ÅÆÁõÆÊ®ô„ÇÑÊ∞óÊåÅ„Å°„ÇíËÅû„ÅфŶ„Äʼn∏ÄÁ∑í„Å´Á∑¥ÁøíË®àÁÇíÁ´ã„Ŷ„Åü„Çä„ÄÅÁõÆÊ®ôË®≠ÂÆö„Çí„Åô„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Çì„Åß„Åô„ÄÇ„ÇÇ„Å°„Çç„Çì„Éì„Ç∏„Éç„Çπ„Åß„ÅÆÂäπÊûú„ÇÑ„Ç®„Éî„ÇΩ„Éº„Éâ„ÇÇ„ÅäËÅû„Åç„Åó„Åæ„Åó„Åü„Åå„ÄÅ„Éó„É©„ǧ„Éô„ɺ„Éà„ř§âÂåñ„Åæ„ÅßËÅû„Åë„Çã„Åì„Å®„Åå„Åô„Åî„Åè¨â„Åó„Åè„Ŷ„ÄÇ
„Åù„ÅÜ„ÅÑ„Å£„Åü„ÅäÂÆ¢Êßò„ÅÆÁîü„ÅÆ£∞„ÇíËÅ¥„ÅфŶ„ÅÑ„Åè‰∏≠„Åß„ÄÅ„Äå„Åì„ÅÆÊôÇÈñì„Çí„Åü„ÅÝ„ÅƉºöË©±„ÅßÁµÇ„Çè„Çâ„Åõ„Çã„ÅÆ„ÅØ„ÇÇ„Å£„Åü„ÅÑ„Å™„ÅÑ„Äç„Å®ÊÄù„Å£„Ŷ„ÄÇÂÆüÈöõ„ÄÅÁÝî‰øÆ„ÅÆË≤ªÁî®ÂØæÂäπÊûú„Å£„ŶÂÆöÈáèÂåñ„Åó„Å´„Åè„Åè„Ŷ„ÄÅ„ÅäÂÆ¢Êßò„Åã„Çâ„Åó„Åü„Çâ‰Ωï„ÇíÊÝπÊãÝ„Å´ÁÝî‰øÆ„ÇíÁ∂ôÁ∂ö„Åô„Çã„Åã„Å®„ÅÑ„ÅÜÂà§Êñ≠„Åå„Åó„Å´„Åè„Åã„Å£„Åü„Çì„Åß„Åô„ÄÇ
そこで、お客様の意思決定の手助けになるものとしてそこでの会話をテキスト化して資料にする、ということにも挑戦しました。
‚Äï‚Äï„Åù„Åì„Åß„ÇÇÁĨ±±„Åï„Çì„ÅÆ„ÇØ„ÉØ„ÉÄ„ÉÜ„Åå„ÅÇ„Å£„Åü„ÅÆ„Åß„Åô„Å≠„ÄÇ„ÄåÂñã„Çã„Çà„ÇäÊõ∏„ÅèÊñπ„ÅåÂêë„ÅфŶ„ÅÑ„Çã„Åã„ÇÇ„Äç„Å®ÊÄù„Å£„Åü„ÅÆ„ÇÇ„Åì„ÅÆÈÝÉ„ÅÝ„Å£„ÅüÔºü
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅØ„ÅÑ„ÄÇË©±„Åô„ÅÆ„ÅØÂæóÊÑè„Åß„ÅØ„Å™„Åã„Å£„Åü„Åë„Å©„ÄÅËÅû„ÅÑ„Åü„Åì„Å®„Çí„Åæ„Å®„ÇńŶ„Äʼnºù„Çè„Çã„Çà„ÅÜ„Å´ÊñáÁ´Ý„Å´„Åô„Çã„ÅÆ„ÅØË㶄Åò„ÇÉ„Å™„Åã„Å£„Åü„ÄÇ„ÇÄ„Åó„ÇçÊ•Ω„Åó„Åã„Å£„Åü„Çì„Åß„Åô„ÄÇ„Åì„ÅÆÁµåÈ®ì„Åå„ÄÅËá™ÂàÜ„ÅƉ∏≠„ÅÆÂ∞è„Åï„Å™„Äå„Åß„Åç„Çã„Åã„ÇÇ„Äç„ÇíËÇ≤„Ŷ„Ŷ„Åè„Çå„ÅüÊúÄÂàù„ÅƉ∏ÄÊ≠©„Åß„Åó„Åü„ÄÇ
‚Äú„Åß„Åç„Çã„Åì„Å®‚Äù„Ç퉪ïÁµÑ„Åø„Å´„Åô„Çã‚îÄ‚îÄÁßÅ„ÅåÂûãÂåñ„Å´„Åì„ÅÝ„Çè„ÇãÁêÜÁî±
¬Ý
‚Äï‚ÄïÂâçÁ´Ý„Åß„Äńǧ„É≥„Çø„Éì„É•„ɺˮò‰∫ã„ÅƉΩúÊàê„ÇíÈÄö„Åò„Ŷ„Äå„Åß„Åç„Çã„Åì„Å®„Åå„ÅÇ„Çã„Äç„Å®ÊÑü„ÅòÂßã„ÇÅ„Åü„Å®„ÅÑ„ÅÜ„ÅäË©±„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åó„Åü„Å≠„ÄÇ„Åù„ÅÆÂæå„ÄÅ„Å©„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å´Áô∫±ï„Åó„Ŷ„ÅÑ„Å£„Åü„ÅÆ„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÅãÔºü
¬Ý
瀬山:1年目の後半、インタビューを繰り返すうちに「これ、もっと効率よくできるんじゃないか」と思い始めました。最初は記事1本作るのに5〜6時間かかっていたのですが、毎回ゼロから考えるのが非効率で。どうすれば短時間で質を保てるかを考え始めたのが、「型化」のスタートでした。
¬Ý
――その「型化」とは、具体的にどんな取り組みですか?
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ǧ„É≥„Çø„Éì„É•„ɺ„ÅÆË≥™ÂïèÈÝÖÁõÆ„ÄÅË®ò‰∫ã„ÅÆÊßãÊàê„ÄÅÁ¥çÂìÅ„Éï„É≠„ɺ„Å™„Å©„ÄÅ„Åô„Åπ„Ŷ„ÇíÊ®ôÊ∫ñÂåñ„ɪÂèØ˶ñÂåñ„Åô„Çã„Åì„Å®„Åß„Åô„ÄÇ„Äå„Å©„ÅÆÈÝÜÁÅ߉Ωï„ÇíËÅû„Åë„Å∞Ê∑±„ÅÑË©±„Ååºï„ÅçÂá∫„Åõ„Çã„Åã„Äç„Äå„Å©„ÅÆË®ÄËëâ„ÅØÂâä„Çâ„Åö„Å´ÊÆã„Åô„Åπ„Åç„Åã„Äç„Äå„Å©„ÅÜ„Åô„Çå„Å∞Âà∂‰ΩúÊôÇÈñì„ÇíÁü≠Á∏Æ„Åß„Åç„Çã„Åã„Äç„Å™„Å©„ÇíÂàÜÊûê„Åó„Ŷ„ÄÅ„Å≤„Å®„ŧ„ÅÆÊâãÈÝÜ„Å®„Åó„ŶËêΩ„Å®„ÅóË溄Åø„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
¬Ý
――その結果、何が変わりましたか?
¬Ý
瀬山:作業効率はもちろんですが、「誰がやっても、ある程度の品質を保ってアウトプットできる」ようになったことが一番大きいです。属人化を防ぎ、仕組みで再現性をつくることができるようになりました。
¬Ý
‚Äï‚ÄïË®ò‰∫ãÂà∂‰Ωú„ÅÆÂäπÁéáÂåñ‰ª•Â§ñ„Å´„ÇÇ„ÄÅÂûãÂåñ„ÅÆÊÑèÁæ©„ÇíÊÑü„Åò„ÅüÂÝ¥Èù¢„ÅØ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÅãÔºü
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄDŽǧ„É≥„Çø„Éì„É•„ɺ‰∏≠„Å£„Ŷ„ÄÅ„ÅäÂÆ¢Êßò„Åå„Åô„Åî„Åè§߉∫ã„Å™„Åì„Å®„ÇíË©±„Åó„Ŷ„Åè„ÅÝ„Åï„Çã„Çì„Åß„Åô„Åå„ÄÅ1ÈıÈñìÂæå„Å´„ÅØ„Åø„Çì„Å™Âøò„Çå„Ŷ„Åó„Åæ„ÅÜ„Çì„Åß„Åô„Çà„Å≠„ÄÇÁßÅËá™Ë∫´„ÇÇ„Åù„ÅÜ„Åß„Åó„Åü„Åó„ÄÅÂñ∂Ê•≠„ÇÇ„ÄåË™∞„Å´„Å©„Çì„ř˩±„ÇíËÅû„ÅÑ„Åü„Åã„Äç„ÇíË®òÊÜ∂„Å´Èݺ„Çä„Åå„Å°„Åß„Åó„Åü„ÄÇ„ÅÝ„Åã„Çâ„Åì„Åù„ÄÅ‚ÄúÂΩ¢„Å®„Åó„ŶÊÆã„Åô‚Äù„Åì„Å®„ÅÆÊÑèÂë≥„Çí„Åô„Åî„Åèº∑„ÅèÊÑü„Åò„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
ÂûãÂåñ„Åô„Çã„Åì„Å®„Åß„ÄÅ„Å©„Çì„Å™‰∫∫„Åß„Çlj∏ÄÂÆö„ÅÆÊàêÊûú„ÇíÂá∫„Åõ„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çã„Çì„Åß„Åô„ÄÇ„Åæ„Åï„Å´„ÄÅÂÖ•Á§æ„Åó„Åü„Å∞„Åã„Çä„ÅÆÁßÅ„ÇÑ„ÄÅÁï∞ÂãïÁõ¥Âæå„ÅƉΩï„ÇÇ„Åß„Åç„Å™„Åã„Å£„Åü‚ÄúÂá°‰∫∫„ÅÆÁßÅ‚Äù„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™‰∫∫„Åß„ÇÇ„ÄÇ„ÅÝ„Åã„Çâ„Åì„Åù‰ªä„ÅØ„ÄÅ‚ÄúÁßÅ„Åå„ÅÑ„Å™„Åè„Ŷ„ÇÇÊàêÊûú„ÅåÂá∫„Ç㉪ïÁµÑ„Åø‚Äù„Çí‰Ωú„Çã„Åì„Å®„Åå„ÄÅ„Éńɺ„ÉÝ„ÇÑÁµÑÁπî„Å∏„ÅƉ∏ÄÁÅÆË≤¢ÁåÆ„ÅÝ„Å®ÊÄù„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
¬Ý
――記録があることで、組織としての「知」が蓄積されるわけですね。
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„Åù„ÅÜ„Åß„Åô„ÄÇ„Åù„Çå„Å´„ÄÅË®òÈå≤„Åå„ÅÇ„Çå„Å∞„ÄÅÂà•„ÅÆË™∞„Åã„Åå˶ã„Ŷ„Çljæ°Âħ„Å剺ù„Çè„Çã„Åó„ÄÅÊñΩÁ≠ñ„ÇÑÊñπÈáù„ÅÆÂà§Êñ≠ÊùêÊñô„Å´„ÇÇ„Å™„Çã„Älj∫∫„ÅÆË®òÊÜ∂„ÅØÊõñÊòß„ÅÝ„Åë„Å©„ÄÅË®ÄË™ûÂåñ„Åï„Çå„Åü„ÇÇ„ÅÆ„ÅØÊ∂à„Åà„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ„Åù„Åì„Å´‰æ°Âħ„ÇíÊÑü„Åò„Ŷ„ÄÅ„ÄåÂûãÂåñ„Äç„Å´„ÅÆ„ÇÅ„ÇäË溄Çì„Åß„ÅÑ„Åç„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
¬Ý
――その思想は、後のマーケティング業務にも引き継がれていくことになりますよね。
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅØ„ÅÑ„ÄÇ„Éû„ɺ„DZ„Å´Áߪ„Å£„Ŷ„Åã„Çâ„ÇÇ„ÄÅ„Ä剪ïÁµÑ„Åø„ÅßÊàêÊûú„ÇíÂá∫„Åô„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜËÄÉ„ÅàÊñπ„ÅØ„Åö„Å£„Å®‰∏ÄË≤´„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ1‰∫∫„ÅÆÈÝ뺵„Çä„ÅßÊàêÊûú„ÇíÂá∫„Åô„ÅÆ„Åß„ÅØ„Å™„Åè„ÄÅ„Éńɺ„ÉÝ„Å®„Åó„ŶÂÜçÁèæÊÄß„ÅÆ„ÅÇ„ÇãÊñΩÁ≠ñ„Çí‰Ωú„Çã„ÄÇ„Åù„Çì„Å™ÊñáÂåñ„Çí‰Ωú„Çä„Åü„Åè„Ŷ„Äʼnªä„ÇÇÂûãÂåñ„ÇíÂú∞ÈÅì„Å´Á∂ö„Åë„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
マーケティング配属後の試練と転機
¬Ý
‚Äï‚Äï„ÄåÔºó„ŧ„ÅÆÁøíÊÖ£¬Æ„Äç„Éńɺ„ÉÝ„Åß„ÅÆ1Âπ¥ÁõÆ„ÇíÁµå„Ŷ„ÄÅ2Âπ¥ÁõÆ„Åã„Çâ„ÅØ„Éû„ɺ„DZ„ÉÜ„Ç£„É≥„Ç∞„Ç∞„É´„ɺ„Éó„Å´Áï∞Âãï„Åï„Çå„Åü„Çì„Åß„Åô„Çà„Å≠„ÄÇ
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅØ„ÅÑ„ÄÅ„Åù„ÅÜ„Åß„Åô„ÄÇÂΩìÊôÇ„ÅØ„Å°„Çá„ÅÜ„Å©Smart Boarding„ÅåÊã°Â§ß„Åó„Ŷ„ÅÑ„ÅüÊôÇÊúü„Åß„ÄÅ„Éû„ɺ„DZ„ÉÜ„Ç£„É≥„Ç∞„Éńɺ„ÉÝ„ÇljΩìÂà∂„ÇíÊ籠Åà„Ŷ„ÅÑ„Åè„Éï„Ç߄ɺ„Ç∫„Åß„Åó„Åü„ÄÇ
¬Ý
――異動して、すぐに活躍できたのでしょうか?
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅÑ„Åà„ÄÅ„ÇÄ„Åó„ÇçÁï∞ÂãïÁõ¥Âæå„ÅÆ2„É∂Êúà„Åè„Çâ„ÅÑ„ÅØÊØéÊó•Ê≥£„ÅфŶ„Åæ„Åó„ÅüÔºàÁ¨ëÔºâ„ÄÇÂâç„Éńɺ„ÉÝ„Å®„Åæ„Å£„Åü„ÅèÈÅï„ÅÜÊ•≠Âãô„ÄÅʱDŽÇÅ„Çâ„Çå„ÇãÊàêÊûú„ÄÅËÄÉ„ÅàÊñπ„Å´ÂúßÂÄí„Åï„Çå„Ŷ„Åó„Åæ„Å£„Ŷ‚Ķ„ÄÇ
¬Ý
‚Äï‚Äï„Å©„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™„Åì„Å®„ÅåÁâπ„Ŵ§ß§â„ÅÝ„Å£„Åü„ÅÆ„Åß„Åó„Çá„ÅÜÔºü
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö1Áï™ÊúÄÂàù„ÅØ„É°„ɺ„É´ÊñΩÁ≠ñ„ÇíÊãÖÂΩì„Åó„Åü„ÅÆ„Åß„Åô„Åå„ÄÅ„Äå„É°„ɺ„É´„ÇíÂá∫„Åó„Ŷ„ÇÇ„Åæ„Å£„Åü„ÅèÂèçÂøú„Åå„Å™„ÅÑ„ÄçÁä∂ÊÖã„Åß„Åó„Åü„ÄÇ„Å©„Çì„Å™‰ª∂Âêç„ÅåÈñãÂ∞Å„Åï„Çå„ÇÑ„Åô„ÅÑ„ÅÆ„Åã„ÄÅ„Å©„ÅÜ„ÅÑ„ÅÜÂÜÖÂÆπ„ÅÝ„Å®„ÇØ„É™„ÉÉ„ÇØ„Åï„Çå„Çã„ÅÆ„Åã„ÄÅ„Åù„ÅÆÊôÇ„ÅØ„Åæ„Å£„Åü„ÅèÂàÜ„Åã„Å£„Ŷ„ÅÑ„Å™„Åã„Å£„Åü„Çì„Åß„Åô„ÄÇ
„Åï„Çâ„Å´„ÄÅËá™ÂàÜ„ÅåÊÄù„ÅÑÊèè„Åè„Äå„Åì„ÅÜ„Åô„Çå„Å∞„ÅÜ„Åæ„Åè„ÅÑ„Åè„ÅÝ„Çç„ÅÜ„Äç„Å®„ÅÑ„Å܉ªÆË™¨„Åå„ÄÅÊï∞Â≠ó„ÅßÊòéÁ¢∫„Å´Âê¶ÂÆö„Åï„Çå„Çã„ÄÇ„Åù„Çå„Åå„Åô„Åî„Åè„Ç∑„Éß„ÉÉ„ÇØ„Åß„Åó„Åü„ÄÇ
¬Ý
――なるほど。マーケティングは“数字で答えが出る”世界ですからね。
¬Ý
瀬山:はい。でも逆に言うと、そこにマーケティングの面白さがあると気づきました。「正解はないけれど、データがヒントをくれる」。自分で仮説を立てて、検証して、修正して、また試す。そのサイクルが回り始めてからは、楽しくなってきました。
――最初に手応えを感じたのは、どんな施策でしたか?
¬Ý
瀬山:既存のお客様へのメール施策ですね。とあるお役立ち資料のご案内をリストに対して送ったところ、今までの開封率や反応率の倍くらいの結果が出たんです。90件以上の資料希望があって、「これは行けるかも」と思いました。
――数字が出ると一気に手応えが変わりますよね。
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„Åù„ÅÜ„Å™„Çì„Åß„Åô„ÄÇÁµêÊûú„ÅåÂá∫„Åü„Åì„Å®„Åß„ÄÅʨ°„ÇÇÂêå„Åò„Çà„ÅÜ„Å™ÊàêÊûú„ÇíÁîü„ÅøÂá∫„Åô„Å´„ÅØ„Å©„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å´„Åó„Åü„Çâ„Çà„ÅÑ„ÅÆ„Åã„ÄÅÁßʼnª•Â§ñ„Åß„ÇÇ„Åß„Åç„Çã„Å´„ÅØ„Å©„ÅÜ„Åó„Åü„Çâ„ÅÑ„ÅÑ„Çì„ÅÝ„Çç„ÅÜ„Å®„ÄÅ„Åù„Åì„Åã„Çâ„Åï„Çâ„Å´„Ä剪ïÁµÑ„Åø„Å´„Åó„Çà„ÅÜ„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜÊÄùËÄÉ„Ååº∑„Åè„Å™„Çä„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„ÇÑ„Å£„ŶÁµÇ„Çè„Çä„Åß„ÅØ„Å™„Åè„ÄÅË™∞„Åß„ÇÇÂÜçÁèæ„Åß„Åç„Çã„Çà„ÅÜ„Å´Ë®≠Ë®à„Åô„Çã„Åì„Å®„Å´„ÄÅ„ÇÑ„Çä„Åå„ÅÑ„ÇíÊÑü„Åò„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
¬Ý
――その後、さらなる転機が訪れたと聞いています。
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅØ„ÅÑ„ÄÇ„Éû„ɺ„DZ„Å´Áï∞Âãï„Åó„Ŷ1Âπ¥Áµå„Å£„ÅüÈÝÉ„ÄÅ„Éńɺ„ÉÝ„É™„ɺ„ÉĄɺ„ÅÝ„Å£„ÅüÂÆáÁî∞Â∑ù„Åï„Çì„ÅåËÇ≤‰ºë„Å´ÂÖ•„Çã„Åì„Å®„Å´„Å™„Å£„Ŷ„ÄÇ„Äå„Åì„Çå„ÄÅÁßÅ„Åå„ÇÑ„Çâ„Å™„Åç„ÇÉË™∞„Åå„ÇÑ„Çã„Çì„ÅÝ„Çç„Å܂Ķ„Äç„Å®„ÄÅËá™ÁÑ∂„Å´ÊÄù„ÅÑ„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
¬Ý
――その時、怖さはなかったですか?
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÇÇ„Å°„Çç„Çì‰∏çÂÆâ„Åß„Åó„Åü„ÄÇ„Åß„ÇÇ„ÄÅ„Åù„Çå„Çà„Çä„ÇÇ„Äå„Éńɺ„ÉÝ„ÇíÊ≠¢„ÇÅ„Åü„Åè„Å™„ÅÑ„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜÊ∞óÊåÅ„Å°„Ååº∑„Åè„Ŷ„ÄÇ„ÅÝ„Åã„Çâ„ÄÅ„Åß„Åç„Çã„Åì„Å®„ÅØÂÖ®ÈÉ®„ÇÑ„Çç„Å܄Ůʱ∫„ÇÅ„Åæ„Åó„Åü„ÄÇÂΩìÊôÇ„ÄÅÂ∏ÇÂÝ¥ÈñãÁô∫„Éńɺ„ÉÝ„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Éû„ɺ„DZ„ÉÜ„Ç£„É≥„Ç∞Ժ܄ǧ„É≥„ǵ„ǧ„Éâ„Ǫ„ɺ„É´„ÇπÊ©üËÉΩ„ÇíÊåÅ„Å£„Åü„Éńɺ„ÉÝ„ÅÝ„Å£„Åü„ÅÆ„Åß„Äńǧ„É≥„ǵ„ǧ„Éâ„ÅÆ„Éà„ÉÉ„ÉóÊàêÁî∞„Åï„Çì„ÅåÂÆáÁî∞Â∑ù„Åï„ÇìËÇ≤‰ºë‰∏≠„ÅØÂ∏ÇÂÝ¥ÈñãÁô∫„Éńɺ„ÉÝÂÖ®‰Ωì„ÅÆ„É™„ɺ„ÉĄɺ„Å´ÊäúÊ좄Åï„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
――具体的にはどんなことをされたのですか?
¬Ý
ÁĨ±±ÔºöÂÆáÁî∞Â∑ù„Åï„Çì„ÅåÊãÖ„Å£„Ŷ„ÅÑ„ÅüÈÄ≤Ë°åÁÆ°ÁêÜ„ÇщºÅÁîªÊ•≠Âãô„Äʼnªñ„Éńɺ„ÉÝ„Å®„ÅÆË™øÊ籠ř„Å©„Çí„ÄÅÂÖ®ÈÉ®Ëá™ÂàÜ„Åß„ÇÑ„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Åó„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Å®„ÅØ„ÅÑ„Åà„ÄÅÁßÅ„ÅØ„Éó„ɨ„ǧ„ɧ„ɺ„Å®„Åó„Ŷ„Åó„ÅãÂãï„ÅÑ„Åü„Åì„Å®„Åå„Å™„Åã„Å£„Åü„ÅÆ„Åß„ÄÅÊúÄÂàù„ÅØÊú¨ÂΩì„Ŵ§ß§â„Åß„ÄÇÂêå„Åò„Éńɺ„ÉÝ„ÅÆÊàêÁî∞„Åï„Çì„ÇÑÁ•û±±„Åï„Çì„ÄÅÂ∞æÊ≤º„Åï„Çì„Å®ÂøÖÊ≠ª„Å´„Å™„Å£„Ŷ‰Ωï„Å®„Åã‰πó„ÇäË∂ä„Åà„Åæ„Åó„Åü„Äljªä„Åæ„Åß„ÄåÂûãÂåñ„Äç„Åó„Ŷ„Åç„ÅüÈÉ®ÂàÜ„ÅØÂäπÁéáÁöÑ„Å´Ë™∞„ÇÇ„Åå„Åß„Åç„ÇãÁä∂ÊÖã„Å´„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åã„Çâ„Åì„Åù„ÄÅ„ÇÑ„Å£„Åü„Åì„Å®„ÅÆ„Å™„ÅÑÊ•≠Âãô„Å´ÊåëÊ඄Åß„Åç„Çã‚Äù‰ΩôÁôΩ‚Äù„Åø„Åü„ÅÑ„Å™ÊôÇÈñì„Åå„ÅÇ„Å£„Åü„ÅÆ„Åã„ÇÇ„Åó„Çå„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ
¬Ý
――ここでも「型化」がキーワードになるんですね。
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅØ„ÅÑ„ÄÇË™∞„Åå˶ã„Ŷ„ÇÇÂãï„Åë„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Åô„Çã„Åì„Å®„ÇÇÈáç˶ńÅß„Åô„Åå„ÄÅ„Åù„ÅÆÁµêÊûú„Äʼnªñ„Å´Èáç˶ńř„Åì„Å®„Å´ÂØæÂøú„Åß„Åç„ÇãÊôÇÈñì„Åå¢ó„Åà„Åü„Çä„ÄÅÂÄã‰∫∫„Å´Èݺ„Çä„Åç„Çä„Å´„Å™„Çâ„Å™„ÅÑÊà¶Áï•„ÅåÊèè„Åë„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çã„Åì„Å®„ÅåÈùûÂ∏∏„Å´Èáç˶ńÅÝ„Å®ÊÄù„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
「リーダーを勝たせる」フォロワーシップと主体性のバランス
¬Ý
‚Äï‚ÄïÂâçÁ´Ý„Åß„ÅØ„ÄÅ„É™„ɺ„ÉĄɺ„ÅƉ∏çÂú®ÊôÇ„Å´„Äå„Éńɺ„ÉÝ„ÇíÊ≠¢„ÇÅ„Å™„ÅÑ„Äç„Å®„ÅÑ„Åܺ∑„ÅÑ˶öÊÇü„ÇíÊåÅ„Åü„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åì„Å®„ÅåÂç∞˱°ÁöÑ„Åß„Åó„Åü„ÄÇ„Åù„Åì„Åã„Çâ„Åï„Çâ„Å´ÊÑèË≠ò„Åå§â„Çè„Å£„Ŷ„ÅÑ„Å£„Åü„Åì„Å®„ÅØ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÅãÔºü
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„Åù„ÅÜ„Åß„Åô„Å≠„Äljª•Ââç„Åã„Çâ„Å™„Çì„Å®„Å™„Åè§߉∫ã„Å´„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åó„Åü„Åå„ÄÅ„Çà„Çä„Éńɺ„ÉÝ„ÅÆ„Åì„Å®„ÇíËÄÉ„Åà„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü„Åì„Å®„Åß„ÄÅ„Äå„Éńɺ„ÉÝ„ÅÆ˪∏„Å®„Å™„Çã„É™„ɺ„ÉĄɺ„Åå„Çà„ÇäÂãï„Åç„ÇÑ„Åô„ÅÑÁí∞¢ɄÇí„ŧ„Åè„Çã„Å´„ÅØÔºü„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Åì„Å®„ÇíËÄÉ„Åà„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Éńɺ„ÉÝ„ÅåÊàêÊûú„ÇíÂá∫„ÅóÁ∂ö„Åë„Çã„Åü„ÇÅ„Å´„ÄÅÁßÅ„ÅØ‚Äúʪë˵∞Ë∑Ø„ÇíÊ籠Åà„Çã‰∫∫‚Äù„Åß„ÅÑ„Çà„Å܄Ůʱ∫„ÇÅ„Åü„Çì„Åß„Åô„ÄÇ
――“滑走路を整える人”とは?
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„É™„ɺ„ÉĄɺ„ÅåÊú¨Êù•„ÇÑ„Çã„Åπ„Åç„Åì„Å®„Å´Èõ܉∏≠„Åß„Åç„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„ÄÅÂúüÂè∞„ÇíÊ籠Åà„Ŷ„Åä„Åè„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Åì„Å®„Åß„Åô„ÄÇ„Åü„Å®„Åà„Å∞„ÄÅÊñΩÁ≠ñ„ÅÆÈÄ≤Ë°åÁÆ°ÁêÜ„ÄÅÈñ¢‰øÇËÄÖ„Å∏„ÅÆÂÖ±Êúâ„ÄÅ„Çø„Çπ„ÇØ„ÅÆÂàÜËߣ„Å™„Å©„ÄÅÊôÇÈñì„Å®Âä¥Âäõ„ÅÆ„Åã„Åã„ÇãÈÉ®ÂàÜ„ÇíÁßÅ„ÅåÊãÖ„ÅÜ„Åì„Å®„Åß„ÄÅ„É™„ɺ„ÉĄɺ„ÅØ„Çà„ÇäÈ´ò„ÅÑ˶ñÁÇπ„ÅßÊÑèÊÄùʱ∫ÂÆö„Åå„Åß„Åç„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çã„ÄÇ„Åù„Çå„Åå„ÄÅ„Éńɺ„ÉÝÂÖ®‰Ωì„ÅÆÊàêÊûú„Å´„ŧ„Å™„Åå„Çã„Å®ÊÄù„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ

――まさにフォロワーシップですね。
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅØ„ÅÑ„ÄÇ„Äå„É™„ɺ„ÉĄɺ„ÇíÂãù„Åü„Åõ„Çã„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜÊÑèË≠ò„ÅåËäΩÁîü„Åà„Ŷ„Åã„Çâ„ÄÅËá™ÁÑ∂„Å®„Åù„ÅÜ„ÅÑ„ÅÜÂãï„ÅçÊñπ„Å´„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åç„Åæ„Åó„Åü„ÄÇËá™ÂàÜ„ÅåÁõÆÁ´ã„Åü„Å™„Åè„Ŷ„ÇÇ„ÅÑ„ÅÑ„Åã„Çâ„ÄÅ„Éńɺ„ÉÝÂÖ®‰Ωì„ÅßÊàêÊûú„ÇíÂá∫„Åó„Åü„ÅÑ„ÄÇ„Åù„ÅÜÊÄù„Åà„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü„ÅÆ„ÅØ„ÄÅ„Åì„ÅÆÁµåÈ®ì„Åå„ÅÇ„Å£„Åü„Åã„Çâ„ÅÝ„Å®ÊÄù„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
¬Ý
――「仕組みを作って回す」「連携させて成果を出す」というお話もありましたが、施策同士の関係性もかなり意識されているとか。
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅØ„ÅÑ„ÄÇÁßÅ„ÅØ„Éû„ɺ„DZ„ÉÜ„Ç£„É≥„Ç∞„Çí„ÄåÁü¢Âç∞„ÅÆÁ∑èÂíå„Äç„ÅÝ„Å®ËÄÉ„Åà„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Å≤„Å®„ŧ„ÅÆÊñΩÁ≠ñ„ÅåÁõ¥Êé•ÊàêÊûú„Å´Áµê„Å≥„ŧ„Åè„Çè„Åë„Åß„ÅØ„Å™„Åè„Ŷ„ÄÅ„ÅÑ„Åè„ŧ„ÇÇ„ÅÆÂ∞è„Åï„Å™ÊñΩÁ≠ñ„Åå„ÄÅÈÅï„ÅÜÊñπÂêë„Åã„ÇâÂêå„ÅòÁõÆÁöÑ„Å´Âêë„Åã„Å£„ŶÈáç„Å™„Å£„Åü„Å®„Åç„Äŧ߄Åç„Å™ÊàêÊûú„Å´„Å™„Çã„Çì„Åß„Åô„ÄÇ
――たとえば、どういった施策の連動があるのでしょうか?
¬Ý
瀬山:たとえば、導入リリースで事例を発信した後に、その内容を使ってメールを送る。さらに共催セミナーでは、その事例をテーマにしたコンテンツを提供する。ひとつひとつの施策は小さくても、それが連動することで「成果が出やすい流れ」が生まれるんです。
¬Ý
――“点ではなく、線でつなぐ”という発想ですね。
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„Åù„ÅÜ„Åß„Åô„Å≠„ÄÇ„Åù„Åó„Ŷ„Åù„Çå„ÇíÂÆüË°å„Åô„Çã„Å´„ÅØ„ÄÅ„ÇÑ„ÅØ„Çä„Ä剪ïÁµÑ„ÅøÂåñ„Äç„Ååʨ݄Åã„Åõ„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇË™∞„Åå„ÇÑ„Å£„Ŷ„ÇÇÂêå„Åò„Çà„ÅÜ„Å´ÊñΩÁ≠ñ„ÅåÂõû„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„ÄÅÁßÅ„Å؉ªä„Åß„ÇÇ„ÄåÂûãÂåñ„Äç„ÇíÁ∂ö„Åë„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
¬Ý
¬Ý
ʨ°„Å™„Çã„ÇØ„ÉØ„ÉÄ„ÉÜÔΩû„Äå„Ç≥„É≥„Éà„É≠„ɺ„É´„Åß„Åç„ÇãÈÝòÂüü„Çí„ÇÇ„Å£„Ů¢ó„ÇÑ„Åó„Åü„ÅÑ„Äç
¬Ý
‚Äï‚ÄïÂâçÁ´Ý„Åß„ÅäË©±„Åó„Åè„ÅÝ„Åï„Å£„Åü‚Äú„Éû„ɺ„DZ„ÉÜ„Ç£„É≥„Ç∞„ÅÆÂûãÂåñ‚Äú„ÅØ„Éńɺ„É݄Ŵ§߄Åç„ÅèË≤¢ÁåÆ„Åô„Çã„ÇØ„ÉØ„ÉÄ„ÉÜ„Åß„Åô„Å≠„ÄljªäÂæå„ÄÅ„Åï„Çâ„Å´ÊåëÊ඄Åó„Ŷ„ÅÑ„Åç„Åü„ÅÑ‚Äú„ÇØ„ÉØ„ÉÄ„ÉÜ‚Äú„ÅØ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÅãÔºü
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅØ„ÅÑ„ÄljªäËÄÉ„Åà„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÅÆ„ÅØ„ÄÅSmart Boarding„Å´Èôê„Çâ„Åö„ÄÅFCE„Å®„Åó„ŶÊèê‰æõ„Åó„Ŷ„ÅÑ„ÇãÊßò„ÄÖ„Å™‰æ°Âħ„ÇíÁü•„Å£„Ŷ„ÇÇ„Çâ„Åà„Çã„Çà„ÅÜ„Å™„ǧ„Éô„É≥„Éà„ÅƉºÅÁÅß„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„ÅØ„ÄÅÁßÅ„Åü„Å°„ÅÆ„Éû„ɺ„DZ„ÉÜ„Ç£„É≥„Ç∞„ÅÆÂèñ„ÇäÁµÑ„Åø„Çí„ÇÇ„Å£„Å®Á§æ§ñ„Å´„ÇDZä„Åë„Çã„Åü„ÇÅ„ÅÆÊñ∞„Åó„ÅÑ„ÉÅ„É£„ɨ„É≥„Ç∏„Åß„Åô„ÄDZïÁ§∫‰ºö„ÅÝ„Åë„Å´Èݺ„Çã„ÅÆ„Åß„ÅØ„Å™„Åè„ÄÅËá™Á§æÁô∫‰ø°„Åß„Ç≥„É≥„Éà„É≠„ɺ„É´„Åß„Åç„ÇãÈÝòÂüü„Çí„ÇÇ„Å£„Ů¢ó„ÇÑ„Åó„Åü„ÅÑ„Çì„Åß„Åô„ÄÇ
¬Ý
――おもしろそうな企画ですね!最後に、どんな人と一緒に働きたいですか?
¬Ý
ÁĨ±±Ôºö„ÅÑ„Å°„Å∞„Çì§ßÂàá„Å™„ÅÆ„ÅØ„ÄÅ„ÇÑ„Å£„ű„Çä‚ÄúÂøó‚Äù„ÇíÊåÅ„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åì„Å®„ÅÝ„Å®ÊÄù„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Åü„Å®„Åà˺™ÈÉ≠„Åå„ź„Çì„ÇÑ„Çä„Åó„Ŷ„ÅфŶ„ÇÇ„ÄÅ„Äå„Åì„Çå„ÇíÈÅîÊàê„Åó„Åü„ÅÑ„Äç„Äå„Åì„ÅÜ„ÅÑ„Å܄ŵ„Å܄Ŵ§â„Åà„Ŷ„ÅÑ„Åç„Åü„ÅÑ„Äç„Äå„Åì„ÅÜ„ÅÑ„ÅÜ„ÇÇ„ÅÆ„Çí‰Ωú„Å£„Ŷ„Åø„Åü„ÅÑ„Äç„ÄÅ„Åù„Çì„Å™ÊÉ≥„ÅÑ„ÇíÊåÅ„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã‰∫∫„Å®‰∏ÄÁ∑í„Å´ÂÉç„Åç„Åü„ÅÑ„Å™„Å®ÊÄù„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
„ÇÇ„Å°„Çç„Çì„ÄÅ„Åù„ÅÆÂøó„Åاâ„Çè„Å£„Ŷ„ÅÑ„Å£„Ŷ„ÇÇ„ÅÑ„ÅÑ„ÄÇ„ÇÄ„Åó„Çç„Äŧâ„Çè„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åè„ÇÇ„ÅÆ„ÅÝ„Å®ÊÄù„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Åß„ÇÇ„ÄÅ‚Äú‰ªä„ÅÆËá™ÂàÜ„ÅØ„Åì„ÅÜÊÄù„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã‚Äù„Å®„ÅÑ„ÅÜËäØ„ÇíÊåÅ„Å£„Ŷ„ÄÅ„Åù„Çå„Å´Âêë„Åë„Ŷ‰Ωï„Åã„Åó„ÇâÂãï„ÅфŶ„ÅÑ„Çã‰∫∫‚îÄ‚îÄË°åÂãï„Ç퉪ïÊéõ„Åë„Ŷ„ÅÑ„Çã‰∫∫„Å´ÊÉπ„Åã„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ
„ÇÇ„Åó„Åã„Åó„Åü„Çâ„ÄÅ„Åù„ÅƉ∫∫„ÅåÁõÆÊåá„Åô„ÇÇ„ÅÆ„Å´„ÄÅÁßÅ„ÇÇÂäõ„Å´„Å™„Çå„Çã„Åã„ÇÇ„Åó„Çå„Å™„ÅÑ„Åó„ÄÅÁßÅËá™Ë∫´„ÅÆ„Éë„ɺ„Éë„Çπ„ÇíÂÖ±Êúâ„Åô„Çã„Åì„Å®„Åß„ÄÅFCE„Å®„ÅÑ„ÅÜÁµÑÁπîÂÖ®‰Ωì„ÇÇ„ÇÇ„Å£„٧߄Åç„Åè„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åë„Çã„Å®ÊÄù„ÅÜ„Çì„Åß„Åô„ÄÇ„ÅÝ„Åã„Çâ„Åì„Åù„ÄÅÂøó„ÇíÊåÅ„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã‰∫∫„ÄÅ„Åù„Åó„Ŷ„Åù„ÅÆÊÉ≥„ÅÑ„Å´Âêë„Åã„Å£„Ŷ„Å°„ÇÉ„Çì„Å®Âãï„ÅфŶ„ÅÑ„Çã‰∫∫„Å®„Äʼn∏ÄÁ∑í„Å´ÊåëÊ඄Åó„Ŷ„ÅÑ„Åç„Åü„ÅÑ„Åß„Åô„ÄÇ
‚Äï‚ÄïÁ¥ÝÊ﵄Åß„Åô„Å≠„ÄljªäÂæå„ÅÆ‚Äú„ÇØ„ÉØ„ÉÄ„ÉÜ‚Äù„ÇÇÊ•Ω„Åó„Åø„Å´„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇÊú¨Êó•„ÅØ„ÅÇ„Çä„Åå„Å®„ÅÜ„Åî„Åñ„ÅÑ„Åæ„Åó„ÅüÔºÅ
¬Ý
瀬山:ありがとうございました!
‚ñÝ„ÅäÁü•„Çâ„Åõ¬Ý
ÔººFCEÊé°Áî®ÊÉÖÂݱ„Äĉ∏ÄÁ∑í„Å´ÂÉç„Å艪≤Èñì„ÇíÂãüÈõ܉∏≠Ôºè¬Ý
Ë©≥„Åó„Åè„ÅØÊé°Áǵ„ǧ„Éà„Çí„Åî˶߄Åè„ÅÝ„Åï„ÅÑ„ÄǬÝ
Êé°Áǵ„ǧ„Éà¬Ý
Êñ∞ÂçíÂêë„ÅëÁâπË®≠„ǵ„ǧ„Éà¬Ý
ÂèñÊùê„ɪÂü∑Á≠ÜÔºöÁ´π‰∏≠¬Ý
 FaCE!本気で挑む、を
FaCE!本気で挑む、を